こんにちは。
アラフォーパパです。
前回は「西洋思想の導入」という題名で記事を書きました。
明治初期には、多くの留学生が西欧諸国に赴き、様々な知識を持ち帰り、日本に影響を与えました。
また、西欧諸国の知識人を御雇外国人として雇い入れることで、直接知識や思想を輸入していきました。
この際、イギリス・アメリカ流の自由主義・功利主義・進化論の思想とフランス流の自由平等・天賦人権の思想の両方が日本へと流入しました。
例えば、フランス流の思想は自由民権運動に大きな影響を与えました。
これらの輸入に大きな役割を果たしたのが、明六社とよばれる民間の近代的学会でした。
福沢諭吉などの有名どころが所属していたことが知られています。
このようにして、明治初期には欧米諸国の思想が日本に輸入され、江戸時代のオランダを通じて得られた知識からの変化が訪れていきました。
今回は、文明開化に伴っておきた出来事についておさらいしていきましょう。
それではご覧ください。

洋風化
江戸時代の武士の様相は、ちょんまげに帯刀、そして羽織袴といった感じでしょうか。
明治政府が1871年にだした散髪脱刀令は、ちょんまげを切り、帯刀しないことを自由にしました。
並行して、洋服、洋食、洋館などの西洋風の風俗が広がっていきました。
1872年には官吏の制服を洋服としました。
頭髪はざんぎり頭になり、食生活でもパン食と肉食が普及し始めました。
洋風建築も、役所・学校・銀行などで導入され、煉瓦造の建物が各地に建てられ始めました。
灯火も洋風となり、ガス灯やアーク灯などが用いられました。
さらには、乗り物も変化しました。
1869年に人力車が発明され、その後馬車が輸入され、銀座を鉄道馬車が通るようになりました。

太陽暦
日本では、明治の初期までは太陰暦が使用されていました。
しかし、1872年に明治政府は従来の太陰暦に変わって、太陽暦を採用することに決定しました。
太陽暦は、地球が太陽の周りをまわる周期を基にして作られた暦で、世界の多くの国で採用されているのはグレゴリオ暦です。
ちなみに太陰暦は、月の満ち欠けの周期を基にした暦です。
結果として、明治5年12月3日(太陰暦)が、明治6年(1873年)1月1日(太陽暦)となりました。
また、七曜制も実施されて、ヨーロッパ並になりました。
しかし、問題点は農業でした。
農業と太陰暦が深く結びついていたことから、農村部では太陽暦への切り替えがかなり遅れました。

新聞・雑誌
廃藩置県後に、新聞や雑誌が発行されるようになりました。
東京を中心としての発行でした。
1870年に「横浜毎日新聞」が創刊されました。
最初の日刊新聞です。
その後は、自由民権運動のときには政治評論中心の新聞が有名になり、自由党系の「朝野新聞」・改進党系の「郵便報知新聞」・帝政党系の「東京日日新聞」などがありました。
これらの新聞などの発行には印刷技術が必要ですが、1870年に本木昌造(もときしょうぞう)が鉛活字の鋳造に成功したことから、近代的な印刷技術が発展しました。

祝日
文明開化の時期は新しいものへと変化することが良いことであるという風潮がありました。
そのため、古くからの伝統的な民俗行事は否定されました。
また、神道を取り入れていましたので、祝祭日は神道的な性格の強い皇室中心の日にちに改められました。
廃止された代表例は、七夕や端午の節句などです。
1873年に制定された祝祭日を羅列してみましょう。
四方拝:1月1日
元始祭:1月3日
新年宴会:1月5日
孝明天皇祭:1月30日
紀元節:2月11日
神武天皇祭:4月3日
神嘗祭:9月17日
天長節:11月3日
新嘗祭:11月23日
神嘗祭は現在も行われており、「天皇陛下の大御心を体して、天照大御神に新穀を奉り収穫の感謝を捧げる祭典」として行われています。
現在では10月15日から始まります。
また、11月3日は現在も祝日で文化の日です。
ただ、天長節とは関連がなく、文化の日は日本国憲法が1946年11月3日に公布されたことを記念して祝日になっています。
11月23日は勤労感謝の日として残っています。
これは新嘗祭が元になっていて、新嘗祭の意味合いが「その年の新穀を神様に供え、収穫を祝う」ということからつながっているということです。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「文明開化の影響」と題して、記事を作成しました。
明治政府は様々な点で、洋風化を目指していきました。
人々に関することでは、散髪脱刀令が大きく関与していると思われます。
また、建物や洋服などは政府に関連したものから導入されていったと考えても間違いではありません。
さらに印刷技術によって、新聞が広がりを見せて、自由民権運動にも影響を与えていきます。
暦については太陽暦にかえることで一気に欧米と揃えていきます。
祝日だけは洋風ではなく、神道的性格の強い皇室中心の日程へと決められました。
明治政府の思惑によって、洋風とするのか、天皇中心の形にするのかといった部分が分けられていった用に感じますね。
ぜひ、繰り返しご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。





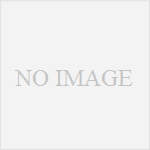
コメント