こんにちは。
アラフォーパパです。
前回は「文明開化の影響」という題名で記事を書きました。
明治政府は様々な点で、洋風化を目指していきました。
人々に関することでは、散髪脱刀令が大きく関与していると思われます。
また、建物や洋服などは政府に関連したものから導入されていったと考えても間違いではありません。
さらに印刷技術によって、新聞が広がりを見せて、自由民権運動にも影響を与えていきます。
暦については太陽暦にかえることで一気に欧米と揃えていきます。
祝日だけは洋風ではなく、神道的性格の強い皇室中心の日程へと決められました。
明治政府の思惑によって、洋風とするのか、天皇中心の形にするのかといった部分が分けられていった用に感じますね。
今回は、欧米諸国との外交関係についておさらいしていきましょう。
それではご覧ください。

列国への通知
明治政府が成立すると、外交の方針を直ちに決めました。
それは、開国和親という方針です。
また、日本の権力者が誰であるのかをはっきりと海外に通告しました。
もちろん、当時の日本の最高権力者は天皇です。
しかし、西欧諸国は、天皇中心の明治政府自体は承認しましたが、高圧的な態度はかわらないままでした。

条約の負の遺産
幕末に徳川幕府が締結した条約については、明治政府はそのまま受け継ぐしかありませんでした。
そのため、不平等な条項を引きつぐこととなってしまいました。
①領事裁判権を外国人に認めること
②関税自主権がないこと
③片務的最恵国待遇を相手国に与えること。
これらを解消していくことが今後の課題となっていました。

帝国主義
19世紀末の西欧諸国は、資本主義的発展により、相互に対立しながら植民地獲得をすすめていました。
これが、帝国主義もしくは帝国主義時代と呼ばれるものです。
日本は、植民地回避をめざし、列強の対立に上手く乗じ、その間に欧米諸国に追いつくために対応しました。
その間、欧米諸国に対しては従属的態度をとりつつも、アジア諸國に対しては高圧的で侵略的な態度を示しました。
これを国権外交といいます。

岩倉使節団
1858年に結んだ安政五カ国条約は、1872年が改定時期になっていました。
日米通商修好条約の13条には「1872年7月4日には条約を改正できる」という文言があります。
そこで、明治政府は1871年10月に政府の首脳を欧米に派遣して条約改正に着手させることにしました。
特命全権大使は、外務卿から右大臣になった岩倉具視で、副使には参議の木戸孝允・大蔵卿の大久保利通・工部大輔の伊藤博文らがつきました。
総勢48名の大所帯となった使節団です。
条約改正の予備交渉のためだけでなく、近代的な欧米諸国の制度や文明の視察および調査も目的としていました。
残念ながら最初の訪問国であるアメリカで日本側の国際交渉の知識欠如が原因となって、希望を受け入れてもらうことができず、改正交渉は打ち切られました。
そのため、2つ目の目的である近代的な制度や文明などを中心にヨーロッパ諸国をまわり、73年9月に帰国しました。
この2年にわたり視察が、明治政府に近代化政策が不可欠であることを痛感させました。
政治面では、独立を維持するためには君主権の強力な独裁体制が必要であることを学び、経済面では、殖産興業政策への注力へとつながり、文化面では仏教界の革命や新聞の開始に大いに影響がありました。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「欧米諸国との関係」と題して、記事を作成しました。
西欧諸国に対して、天皇中心の明治政府であることは承認してもらえました。
しかし、高圧的な態度には代わりはありませんでした。
また、徳川幕府のときに結んだ不平等条約が負の遺産となり、大きな問題として残っていました。
条約の改正のために岩倉使節団を派遣しましたが、国際的な交渉の知識がなかったことから、うまくいきませんでした。
ただ、使節団を派遣したことから、政治面・経済面・文化面における近代化政策に対して大きな影響を与えることができました。
明治政府は、独立を維持するために近代化政策に力を入れ、欧米諸国と同様の帝国主義を執り行い、アジア諸国に対して高圧的な態度を示していくことになります。
ぜひ、繰り返しご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。




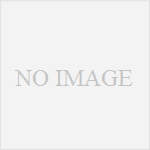
コメント